「有事の円買い」は過去の常識?混迷する中東情勢と円売りの新潮流

【画像出典元】「Yellow_man/Shutterstock.com」
監修・ライター
「有事のたびに円が買われる」そんな為替市場の常識が、静かに、しかし確実に崩れ始めています。これまで、戦争やテロ、災害などの「有事」が起きると、日本円は「安全資産」として買われてきました。市場関係者の間では、それが当然の反応とされていたのです。
しかし近年は、その図式に異変が生じています。ウクライナ侵攻、中東の軍事衝突、紅海の航路混乱といった世界的リスクが高まる中で、なぜか円は買われず、むしろ売られる場面が目立つようになってきました。
なぜ「有事の円買い」が起きなくなったのでしょうか?本記事では、かつてのセオリーが通用しなくなった理由を解き明かしながら、これからの為替リスクとの付き合い方を考えていきます。
「有事の円買い」とは何か?その歴史と背景
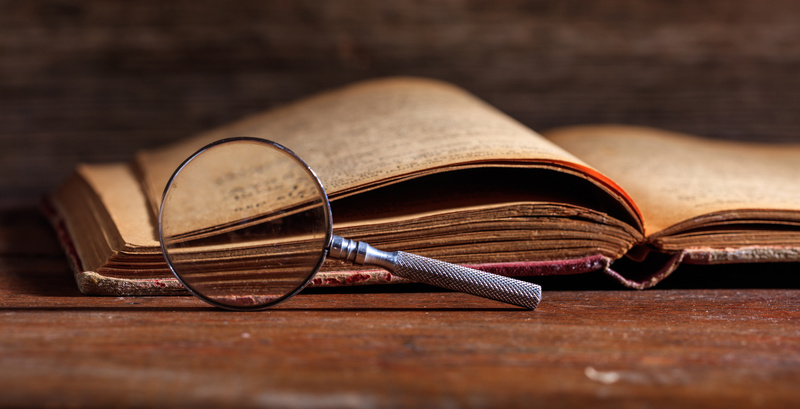
「有事の円買い」とは、世界で大きなトラブルが起きた時に、日本円が買われて円高になる現象を指します。なぜそうなるのか、まずはその背景を見ていきましょう。
「有事の円買い」誕生の背景と仕組み
「有事の円買い」とは、戦争やテロ、金融危機といった世界的なリスクが高まった時に、市場で日本円が買われる傾向のことです。これは長年にわたって、為替市場の常識のように語られてきました。
その理由のひとつが、日本の経済が長らく安定していたことです。日本は貿易で得るお金(経常収支)が黒字で、たくさんの外国資産を保有する「債権国」として知られてきました。また、金利が低かったため、円で借りて他国通貨に投資する「円キャリートレード」が普及し、リスクが高まるとその資金が円に戻ってくる動きがありました。
こうした背景から、世界に不安があると「とりあえず円を買おう」という投資家の動きが定着していたのです。
過去の主要な有事と円の動き
実際に「有事の円買い」が起きた例はいくつもあります。たとえば、2001年のアメリカ同時多発テロ事件では、株価が大きく下がる中で円が買われ、円高が進みました。また、2008年のリーマンショックでも世界的に信用不安が広がると、投資家はリスクを避けるために円を買う動きに出ました。
2011年の東日本大震災の時も、一時的に円が急上昇しました。これは保険金の支払いや日本企業の資金調達などが理由とされ、やはり有事に円が買われる現象のひとつと考えられています。
こうした過去の出来事では、「リスクが高まる=円高になる」というパターンが何度も見られました。それが「有事の円買い」という考え方の根拠になっていたのです。
なぜ今、「円売り」が起きているのか?有事に買われない理由とは
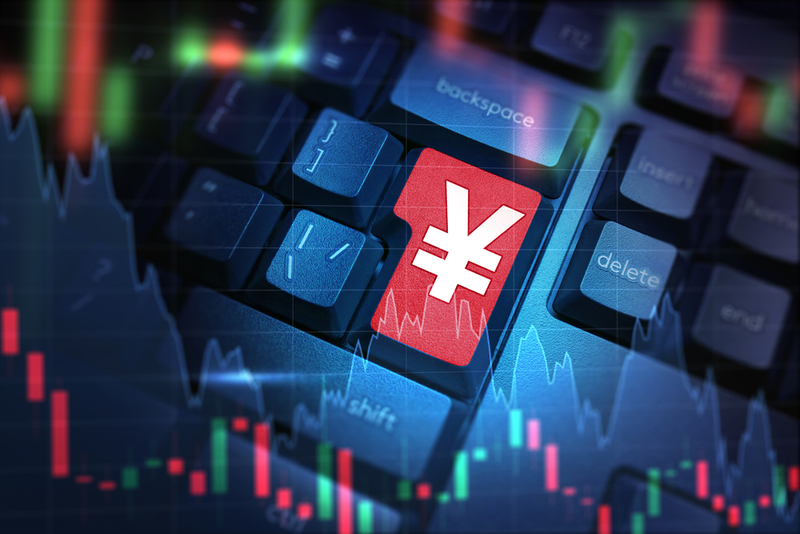
以前は「有事の円買い」が当たり前でしたが、最近はその逆の「円売り」が目立っています。なぜこうした変化が起きているのか、背景にある経済の流れや国際情勢を見てみましょう。
日米金利差の拡大と円安圧力
今の為替市場では、「日米の金利差」が円安を引き起こす大きな要因になっています。アメリカではインフレ対策として、中央銀行(FRB)が政策金利を大きく引き上げました。一方、日本銀行は長らく金利をほぼゼロのままにしており、この差が広がっているのです。
投資家にとっては、金利が高い国の通貨を持つ方が得になります。そのため、ドルを買って円を売る動きが強まり、結果として円安が進みやすくなっています。たとえ世界でリスクが高まっても、金利の魅力がドルに集中すれば、以前のように円が買われるとは限らなくなっているのです。
日本の経常収支・国力イメージの変化
かつて日本は、輸出が強く経常収支が黒字という「経済的に安定した国」として評価されていました。そのため、有事の際には円が「安全通貨」と見なされやすかったのです。
しかし最近は、エネルギー価格の上昇や輸出の低迷により、貿易赤字が続くようになりました。さらに、少子高齢化や膨らむ政府債務もあって、日本経済に対する信頼は以前よりも揺らいでいます。
こうした要素が重なり、「日本の円は本当に安全資産なのか?」という見方が市場では広がっています。その結果、有事であっても円が積極的に買われるとは限らず、逆に売られる動きが目立つようになってきたのです。
中東情勢など地政学リスクと円の反応
たとえば2024年以降に起きたガザ地区での軍事衝突や、紅海での海上輸送ルートの混乱など、中東情勢は世界経済にとって大きな不安要因になっています。こうした地政学リスクが高まると、かつては「円買い」の動きが出るのが通例でした。
ところが最近では、「リスク=ドル買い」という反応が強まっています。アメリカの軍事的な影響力や経済規模への安心感から、資金が円よりもドルに向かう傾向が出ているのです。
また、地政学リスクが長期化・複雑化する中で、為替市場では円よりも他の選択肢を重視する流れが強まっているともいえます。このように、「有事の円買い」はもはや当たり前ではなくなってきています。
今のうちに何を備えるべきか?円安時代の資産防衛策とは

「有事の円買い」が当たり前でなくなった今、私たちは為替市場をどう見ていけばいいのでしょうか。最後に、今後の為替動向を読み解くうえで意識したい視点や、個人でできる備えについて考えてみます。
有事のたびに円高になる時代は終わった?
近年、「安全通貨」とされてきた日本円の立場に変化が見られます。これまでのように、世界で不安が高まると自動的に円が買われるとは限らなくなってきました。
代わりに、米ドルが「より強い安全資産」として選ばれる場面が増えています。これは、アメリカの高金利や経済力、そして世界中の投資家がドル建て資産を持っていることが背景にあります。
もちろん、すべてのケースで円が売られるわけではありませんが、少なくとも「有事=円高」という過去のセオリーが通用しなくなってきているのは確かです。これからは、その前提を見直すことが求められます。
円安局面での資産防衛・分散投資のヒント
円安が続くと、海外製品の値上がりや生活コストの上昇に繋がります。個人レベルでも「円の価値が下がるリスク」への備えが重要になってきました。たとえば、外貨建て資産を一部ポートフォリオに組み込む方法があります。具体的には、米ドル建ての「MMF(マネー・マーケット・ファンド)」や「米国債ETF(例:AGGやTLT)」などは、為替リスクに強く、一定の安定感があります。
また、成長性を狙うのであれば、「S&P500」や「全世界株式(例:VT)」といったインデックス型海外ETFを積立運用するのも一案です。少額から購入でき、長期的にリスク分散を図ることができます。さらに、インフレヘッジとして「金(ゴールド)」への投資も有力です。ネット証券で買える「金ETF(例:GLDやIAU)」や、国内取引所で上場している金価格連動型の投信などを活用する方法があります。
不動産については、ハードルはやや高いものの、インフレや通貨下落に強いとされる実物資産として根強い人気があります。海外REITや国内賃貸用不動産、クラウドファンディング型不動産投資など、形を変えた選択肢も増えています。
大切なのは、ひとつの通貨や資産に依存しすぎないことです。リスクを分散するという意識が、今の為替環境では何よりも「安心」に繋がります。
為替相場は何で動くのか?本質的な見方
為替相場は、金利差や経済指標だけで動いているわけではありません。投資家たちの「心理」や「予想」も大きな影響を与えます。たとえば、ある国の情勢がニュースで大きく報道されるだけでも、その通貨が買われたり売られたりすることがあります。
また、短期的には感情や不安に左右されやすく、長期的には経済の実力(ファンダメンタルズ)に近づいていくという特性があります。つまり、為替を読むには「経済の仕組み」と「人の行動心理」の両方を見る必要があるのです。単純な公式では説明できないからこそ、広い視野で考える姿勢が重要になります。
まとめ
かつて「有事に強い通貨」として信頼されていた日本円。その常識が揺らぐ今、私たちは為替の動きを「過去の延長」で捉えるのではなく、変化の兆しから未来を見通す視点を持つべきなのかもしれません。
投資も生活も、通貨に守られるだけの時代は終わりました。これからは、「通貨から自分を守る」発想が求められる時代です。
当たり前が当たり前でなくなった時、次に動くのは自分自身です。凄まじいスピードで変わりゆく世界で柔軟に備えを整えることが、明日の安心へと繋がっていくのではないでしょうか。
※資産運用や投資に関する見解は、執筆者の個人的見解です。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。












