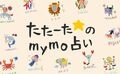たった月8000円が将来を左右!?iDeCoの枠拡大による将来の差は?

2024年12月からiDeCoの枠が「小幅拡充」

2024年1月はNISA制度の大幅拡充でスタートしましたが、12月には「小幅拡充」される制度があります。それはiDeCo(個人型確定拠出年金)です。
iDeCoは、老後の年金の上積みを図る目的で掛金を拠出すると、所得税・住民税が軽減され(掛金が全額所得控除。NISAにはない)、運用収益は非課税(NISAと同様)となります。受取時の税負担は、軽いか非課税受け取りが可能となる(加入年数、受取額等の条件による)仕組みで、全体としてはかなり有利な制度です。
2024年8月時点では、342万人が加入しており、NISAと並んで老後資金準備の大きな柱となっています。
このiDeCo、NISAほどではないものの、限度額が「小幅拡充」されます。しかし、拡充幅が小さいからとスルーしているともったいない改正かもしれません。
公務員と、会社員で企業年金ありの人が対象
iDeCoは働き方や会社の企業年金の有無で拠出限度額が変わります(そこがちょっとややこしい!)。
今回、変更があるのは、公務員と会社員で企業年金制度がある人達です。今まで制度の種類によって月の上限額が20000円か12000円に分かれていたのですが、今回月20000円に引き上げられ統一されます。
ただし、企業年金制度とiDeCoはひとつの非課税枠を共用しているという考え方から、以下の計算式のチェックも行われます。
(月55000円)−((企業年金の他制度掛金相当額)+(企業型確定拠出年金の掛金額))
※企業年金制度の他制度掛金相当額:社内制度全体で金額が1つ決まり、イントラネット等で開示される
※確定拠出年金の掛金額:企業型の確定拠出年金を実施している場合の、個人ごとの掛金額。サポートHPにログインすると確認できる
上記の計算をしてみた時、計算式の結果が20000円より大きい場合は、iDeCo枠は月20000円となります。20000円より少ない場合は、その数字がiDeCoの掛金枠となります。
例えば公務員の場合、(55000)−((8000)+(0))=47000円となり、月20000円の引き上げを全額活用できる、ということになります。民間企業の場合、一般には公表されていませんので、各自社内情報を調べる必要があります。
今回、変更がない人もいます。以下の人たちです。
・自営業者や20歳以上の学生(国民年金の第1号被保険者):月68000円まで
・会社員や公務員の配偶者で専業主婦(夫)
(国民年金の第3号被保険者):月23000円まで
・会社員で企業年金がない人(※):月23000円まで
※退職金制度、中小企業退職金共済制度などは企業年金ではない
これらの人達は既に月20000円より大きい枠があり、そのままとなります。
枠縮小の可能性もある…が確率は低いか

ところで、計算式をよく見ると分かりますが「(他制度掛金相当額)+(企業型の確定拠出年金の掛金額)」が月35000円を超えると、iDeCoの拠出枠は月20000円以下となってしまいます。この場合、その差額となった月20000円未満の数字が、2024年12月以降の新しい限度額となります。可能性としては現状より枠が減ってしまうかもしれないのです。
とはいえ、確定給付企業年金の統計情報などを見る限り、月35000円以上になるケースは多くないと見られており、ほとんどの会社員(企業年金あり)は月20000円まで「小幅拡充」になると思われます。
ただ、会社の企業型の確定拠出年金のみを実施している会社で制度が充実している場合、月35000円を超える可能性があります。詳しくはサポートHP(金融機関のサイト)で確認してみてください。
とはいえ、枠が小さくなってしまう人は見方を変えれば「会社がたくさんの掛金額を用意し、企業年金制度で老後の備えを充実させている」ともいえます。既にある社内制度をよく知る機会としてみてください。
たかが月8000円?30年後には500万円の差になるかも!?

ここまでややこしい説明をしてきましたが「仕組みが複雑な上に、月8000円位の枠拡大?NISAなら年360万円も投資できるのに?」と思う人もいるかもしれません。
NISAと比べれば、枠の拡大は小幅なので見逃されがちですが、「たかが月8000円、されど月8000円」です。もし、35歳の人がこの8000円の掛金増額を行い、65歳までの30年積み立てをしたとします。
65歳の段階で上乗せした元本だけでも288万円になります。公的年金運用などの利回りに近い数字として、年3.5%の運用実績が確保されたとすると、最終受取額の増額は508万円にもなるのです。
ちなみに20%相当が所得税・住民税の軽減額だと仮定すれば、掛金288万円の2割にあたる57.6万円も節税できたことになります。これも大きな違いです。
もし、増額の余裕があるなら(NISAの積立投資額をシフトするのも検討の余地あり)、月8000円の増額手続きをしてみてください。
今は月8000円の増額は難しい、という人は、一度節約体制の見直しをして、増額の余地がないか検討してみましょう。定期的な家計の見直しは、緩んでいた財布を引き締め、ムダづかいをあぶり出すチャンスかもしれません。
それでも増額が難しい場合は、将来のキャリアアップの際に、iDeCoの加入や増額を検討してみてください。老後の不安を解消するきっかけとして、iDeCoの活用は大きく役立つはずです。