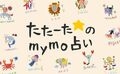“最強の高卒”が稼ぐ時代に、学歴獲得は本当に投資なのか!?

【画像出典元】「Roman Samborskyi/shutterstock.com」
監修・ライター
少子化がドンドン進む日本。大学への入学希望者総数が、大学の入学定員総数を下回る状況がここ数年続いている。大学全入時代ってわけである。その一方で、大学の試験の答えなど生成AIさんに聞けば、アッという間に解答だ。難関大学への人気は、さらに加熱するとは思うが…いつまでそんなことを続けるのか!? お金をいっぱいかけて大学へ行く時代って終わってないか!?それって浪費じゃない!?とワタシ(中村修治)は、思う。
最早、大学へ行くことが成功ではない!!
日本はOECD加盟国の中でも、依然、高い高校進学率を誇っている。しかし、大学進学率は、平均以下。OECDの調査対象30カ国の中で21位で48%である。これはOECDの平均よりも約10ポイントも低く、隣国の韓国よりも低い。※世界で第何位?-日本の絶望 ランキング集 (中公新書ラクレ 800)より
一方で、高等教育費(義務教育以上の教育費)に国や自治体がどれだけ費用の負担をしているのかの割合は、OECD33カ国の中で、日本は、ワースト2位。高等教育費の32%しか財政による支出はされていないのが現実。この30年間、所得が一向に増えない中、物価と授業料だけが上がる。大学進学率が落ちていくのも当然である。
ちなみに、東京大学が行っている「学生生活実態調査」によると、2021年の東大生の親の70%以上が、年収750万円以上、50%以上は年収が950万円以上らしい。親にそれだけの収入がないと、難関大学には入れないということである。
金持ちの子息しか、大学に行けない。
金持ちの子息しか、難関大学にはいない。
この状況を考えると、最早「大学へ行くことが成功の道」ではない。
大谷翔平も藤井聡太も大学など行ってない。
生成AIの進化は圧倒的だ。ChatGPTやClaudeを使えば、検索からアイデア生成、文章構成まで一瞬で完了。その一方で、「記憶力重視」の勉強やマークシート試験中心の教育って、完全に時代遅れである。
大谷翔平は「高卒」でメジャーリーグを圧倒している。
藤井聡太は「中卒」で将棋界のすべてのタイトルを総なめにしている。
この二人の名前を出すだけで、もはや「学歴」や「偏差値」で人の価値を計ることの無意味さが浮き彫りになる。
もちろん、彼らが特別な才能を持っていたことは否定しない。だが、それ以上に見逃してはいけないのは「早期に進路を決め、ひとつの道に集中できた」ことのアドバンテージだ。
彼らは、大学受験のために参考書と向き合い「あと◯点で〇〇大学に届く」といったゲームには参加していない。その時間のすべてを、自分が選んだ道を歩むことに注いできた。結果、世界に通じる実力と成果を手にした。
一方、いまの日本の高校生たちの多くは、18歳になるまで「進路を決めてはいけない」とすら思い込まされている。何になりたいかも分からないまま、大学受験のルールに従い、模試の偏差値に一喜一憂する。それが「正しい青春」だとされた時代は、もう終わりにしたほうが良い。
大学受験制度の問題は、「何を学びたいか」よりも「どこに入れるか」が先に立つ点にある。高校生活の多くを「選択肢を広げるため」に消費し、選び終えた瞬間に熱が冷める。入学してから燃え尽きる学生も多い。
でも本来、学びとは、選択のあとに始まる“深まり”のはずだ。いま必要なのは、「大学に行くかどうか」ではなく、「どこで、誰と、どんなふうに学ぶか」という問いを、もっと早くから許される社会である。そして、「大学に行かない選択」を貧困や失敗と結びつけない風土である。
“最強の18歳”を目指そうぜ!!
大谷翔平が「高卒」であることを誰も馬鹿にしない。
藤井聡太が「中卒」であることを誰も軽視しない。
むしろ、「すごい」と素直に言える。
この価値観こそが、未来を明るくすると思う。
子どもたち一人ひとりが「この道で勝負したい」と思えた時、大学は選択肢のひとつであって、目的ではない。そこに偏差値や受験戦争は不要だ。大谷や藤井のような突出した天才を育てよ!!とは、自分を棚に上げて言えない。ただ「自分の人生は自分で選べる」という実感を持った若者が、一人でも多くなる社会にすべきだと思う。
ワタシは、マークシート型の共通一次試験が始まった頃に大学受験を経験した生粋の昭和の爺さんである。小学5年生の時に、詩人になりたいと言っていた。大学には、小説家になるために進学した。なんも書けなかったけど、いまこうして、こんな雑文を書かせてもらっている。紆余曲折はあったものの、早めにひとつの道を歩き出した結果である。ワタシが令和の高校生であったなら、間違いなく「最強の18歳」を目指している。受験勉強の答え合わせをやっている場合ではないと焦りまくっているはずである…。