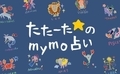住宅ローンの繰り上げ返済をしていい人といけない人、その理由は?

【画像出典元】「Osadchyi_I/Shutterstock.com」
目次
貯蓄をしたい、無駄な支出を抑えたいといった家計の見直し。その代表格の1つが住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済です。いずれもローンの契約内容やタイミング次第では大きな節約につながります。今回は住宅ローンの繰り上げ返済について、「適したタイミングはいつか?」「繰り上げ返済を行うならいくらぐらいが良いのか?」など、繰り上げ返済の仕組みから実践方法まで確認していきましょう。注意点もありますので、参考にしてください。
住宅ローンの繰り上げ返済とは
毎月コツコツ住宅ローンの返済をする中で、ボーナスや臨時収入があった際に借入残高の一部または全部を前倒しで返済することを「繰り上げ返済」といいます。そして、繰り上げ返済の方法は「返済期間短縮型」と「返済額軽減型」の2つがあります。
「返済期間短縮型」
前倒しで返済した分、返済期間を短縮させる返済方法です。下記のイメージ図のように、まとめて返済した分、期間が短くなります。それに伴う利息も支払う必要がなくなります。通常、返済額軽減型よりも利息軽減効果は大きくなります。ただし、毎月の返済額が変わらないので、その後の家計管理を行う上で、繰り上げ返済をした効果を実感しにくいかもしれません。

「返済額軽減型」
一方、返済額軽減型は、返済期間は変わりませんが、毎月の返済額を少なくする返済方法です。繰り上げ返済を行った直後から返済額がその分少なくなるため、繰り上げ返済の効果を感じやすいメリットがあります。

繰り上げ返済をしていい人、いけない人、判断のポイントとその理由は?
繰り上げ返済は大きな利息軽減効果が期待できるため、積極的に行う人も少なくありません。特に最近はネットで手数料が無料(または低額)、かつ少額からこまめに返済できるため、少しでも余裕資金ができたら繰り上げ返済に回している人も少なくありません。当初予定していた利息負担額がどんどん減っていくため、繰り上げ返済を何よりも優先したい気持ちもよく分かります。ただし、注意点もあるため、シミュレーションを通して確認したいと思います。
・当初借入元金 2000万円(ボーナス返済なし)
・当初借入期間 25年
・借入金利 1.5%(全期間固定)
・月々の返済額 7万9987円
上のようなローンを組んでいる人が1年後に100万円繰り上げ返済を行った場合、どうなるでしょうか?「返済期間短縮型」、「返済額軽減型」それぞれ確認します。

「返済期間短縮型」の場合、100万円の繰り上げ返済で40万円以上の利息負担が軽減されます。よって、「100万円で40%の利回り。他の金融商品に投資するよりかなり有利」という考え方をしがちですが、これは要注意です。
確かに銀行預金の金利は超低金利です。株式や投資信託は値上がり益や配当(分配金)が魅力ですが、値下がりするリスクもあります。「40%の利回り」は大変魅力的ですが、住宅ローンはそもそも「負債」です。株式や投資信託で行う資産運用とはまったく科目が異なるのです。
貯蓄や投資は自分の財産として管理・運用をしていきますが、もし100万円を住宅ローンの繰り上げ返済に使うと、その100万円は手元から無くなってしまいます。「資産を増やす」行為と「負債を減らす」行為は全く別物として考えておく必要があります。
例えば繰り上げ返済をした後に大きな病気をして多額の治療費が必要になるかもしれません。車が故障し買い替えることになるかもしれません。そんな場合にまとまった資金がなければ、フリーローンやカーローンなどを通してお金を借りることも考えられます。
住宅ローンは土地や建物が担保として高く評価されることもあり、各種ローンの中で最も金利の低いローンです。積極的に「最も低いローン」を繰り上げた結果、「高い金利のローン」を借りることになっては本末転倒です。
繰り上げ返済により住宅ローンの金利負担を減らすという観点だけではなく、家計の状況や資産の状況などに視野を広げて判断をしていくことが大切です。
ここまでをまとめますと、「繰り上げ返済をしていい人」は以下のようになります。
・生活費の数カ月分の貯蓄(金融資産)があり、毎月一定の貯蓄もできている
・予期せぬ出費が生じてもある程度対応可能である
・教育費、車の買い換えなど今後のライフプランを明確にしている
繰り上げ返済の適した金額は収入や貯蓄状況によって異なりますが、目先数年の大きな支出を考慮しながら、無理のない範囲内で返済することを意識してください。
「繰り上げ返済をしてはいけない人」は、繰り上げ返済をしていい人の逆となります。手元の金融資産が少ない時に積極的に繰り上げ返済を行うことはあまりおすすめできません。
また、住宅ローンを組んでいる人は通常、団信(団体信用生命保険)に加入しています。返済中に契約者が亡くなった場合はローン残高が保険で返済されることになります。よって住宅ローンを組んだ際に、団信を踏まえ死亡保険の解約や減額など、保険の見直しを行う人も多くいます。
このような場合、住宅ローン残高があることが、ある意味「死亡保障」としての役割を担っているのです。リスク管理の1つとして契約者が死亡するというシナリオも頭の片隅に入れておいてください。そういった時のためにも一定の資産を形成しておくことは大切です。これも繰り上げ返済の利息軽減効果ばかりに目を向けてはいけない理由の1つです。
繰り上げ返済のタイミングは早い方がお得?

繰り上げ返済を行う上での注意点について触れましたが、それらを意識しながら、いざ繰り上げ返済を行う場合、どのタイミングで行うのが良いでしょうか?
住宅ローンの仕組み上、繰り上げ返済は「早ければ早い方が良い」です。金利はローン残高に対してかかるため、ローン残高が多い場合に繰り上げ返済を行った方が金利の負担軽減効果は大きくなります。
例えば、先の例は1年後に100万円繰り上げ返済を行った効果を紹介しましたが、もし1年後ではなく10年後に100万円を繰り上げ返済すると利息軽減効果は以下のようになります。
<利息軽減額>

「返済期間短縮型」、「返済額軽減型」どちらも10年後に繰り上げ返済を行うより、ローンを組んで1年後に行う方が利息軽減効果が大きいことが分かります。
ただし、多くの方が住宅ローンを組む際に頭金や諸費用を支払っています。その他、新たな生活を送る中で何かと出費がかさみ、住宅取得後しばらくは金融資産が少なくなっている場合も多いのではないでしょうか。
先に触れた注意点と重なりますが、利息軽減効果が大きいからと、繰り上げ返済にこだわらないでください。コツコツ資産を貯めながら、余裕がある際は早めに繰り上げ返済を行っていく。例えば「毎月3万円は必ず貯金。残業代などで余裕がある場合は繰り上げ返済に回す」といった各家庭に応じたルールを作るのが良いかもしれません。
1つの節目は住宅ローン減税終了後
繰り上げ返済を行う最も良いタイミングの1つは「住宅ローン減税」が終わってからです。住宅ローン減税はローンを組んだ年によって控除率や期間等が異なりますが、現在は、新築住宅の場合、ローン残高の0.7%が13年間に渡り税額控除となります。
例えば年末時点で2000万円の残高があれば所得税・住民税の負担が14万円も減るのです。非常に大きな減税効果であるため、住宅ローン減税期間中はお金を貯めることを優先して、ローン減税が終了した後に繰り上げ返済を行っていくというのも賢明なプランとなります。
なお、ローン残高には上限があります。省エネ性能等に応じて細かい定めがありますが、例えば「省エネ基準適合住宅」の場合、2024年と2025年入居分については3000万円まで対象となります。また新築のうち、一定の省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は2024年より控除期間が13年ではなく10年となりました。
繰り上げ返済を行うなら、利息軽減効果の大きい「返済期間短縮型」が良い?
返済期間を短縮する方が利息軽減効果が大きいため、「繰り上げ返済を行うなら返済期間短縮型」と判断するのは正しいでしょうか?いえ、「返済額軽減型」にするメリットもあるので、利息軽減効果だけで判断しないでください。
例えば、「家を買ってから生活がギリギリ。30年以上のローンを組んで老後が心配」こういった声をよく聞きます。夏・冬の賞与などを繰り上げ返済に充てて、精神的にも楽になりたい、少しでも多く利息負担を減らしたいという気持ちもよく分かります。
ただし、利息軽減効果では劣るものの「返済額軽減型」にすることで月々のローン返済額が少なくなることの方が、家計にとってプラスに働くケースもありそうです。
例えば、月5000円返済額が軽減されれば、その分、iDeCoに加入する、または掛金を増額することで老後資産づくりを行うことができます。iDeCoに限らず、投資信託や外貨預金、純金積立など、気になる投資商品があっても家計収支に余裕がないため実践できていないという人もいるでしょう。
その時過ごす「時間」の価値にも目を向けて
投資は「分散投資」「長期投資」が原則です。いくつかの投資対象に分散させて長期間運用することで大きな成果を得やすいのです。よって、「返済額軽減型」の繰り上げ返済を行うことで月々余裕が生まれた分は積立投資に回すといった考え方もできます。
「時間」に目を向けることも忘れないでください。住宅を購入して住環境が良くなったとしても、月々のローン返済で家計に余裕がなく、家族で外食や旅行を楽しむ機会がすっかり減ってしまったというケースもあります。その間に子供はどんどん大きくなり、気付けば部活動や友人との時間を優先するようになり、家族全員で過ごす時間が減ってしまったということにもなりかねません。
子供がいない場合も同様です。時間は日々流れており、私たちは1つ1つ年齢を重ねていきます。今しかできないこともたくさんあります。「月々の返済額が減ることで余裕が生まれたので習い事を1つはじめたい。」こんな考え方も素敵ですよね。
家計、収支、ライフプラン、全体のバランスを大切に

ここまで述べてきたことをまとめると以下のようになります。
・繰り上げ返済を早く行うことで利息の負担を減らすことができる
・「返済期間短縮型」「返済額軽減型」それぞれの特徴を踏まえ適した返済方法を
・ローンを減らすことが最優先ではない。資産形成や今の時間も大切に
皆さん、一度はオセロゲームをしたことがあるのではないでしょうか?白と黒の石を使い、相手の色を挟むと自分の色に変わるため、ボード上を自分の色が増えるようにと必死に相手の色をひっくり返していると・・・終盤、角を取られ、一気に相手の色が多くなり結局負けてしまう。そんな経験はありませんか?
オセロゲームは住宅ローンの繰り上げ返済によく似ている気がします。目先の枚数ばかりにこだわらず、相手の様子、全体の流れをゆっくり捉えながら落ち着いて対応していくことが大切です。
長く続いたゼロ金利政策から日本は脱し、徐々に利上げを行う方向に転じています。特に変動金利の人は利上げの影響を受けるため「少しでも早く繰上げ返済をして負担を減らそう」「金利が上がる影響をできる限り回避しよう」と思う人も多いでしょう。
もちろん早めに繰上げ返済を行うことも大切ですが、そればかりに気を取られていると思わぬ落とし穴が待っているかもしれません。しっかり先を見据えながら上手に繰り上げ返済を行ってください。
住宅ローンの繰り上げ返済に関するQ&A
Q.期間短縮型の繰り上げ返済を行い、ローンの残り期間が10年未満になっても住宅ローン控除は適用できますか?
A.償還期間で10年以上あれば大丈夫です。住宅ローン控除は10年以上のローン期間が条件ですが、この10年は借入当初から返済までの期間を指します。よって、期間短縮型の繰り上げ返済を行い、残りの期間が10年未満になっても当初から10年以上あれば引き続き住宅ローン控除を適用することはできます。
Q.全期間固定金利の住宅ローンですが、繰り上げ返済をしてもよいですか?
A.一般的に「変動金利+繰り上げ返済」が相性が良いとされています。変動金利の場合、将来金利が上昇する可能性があるため、低い金利で借りて積極的に繰り上げていくというプランです。「固定金利+繰り上げ返済」はミスマッチという指摘もありますが、将来金利が上昇しないという安心感を得ながらも余裕があれば繰り上げ返済をしたいという考え方は決して間違いではありません。ぜひ検討してください。