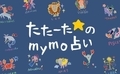長期金利が1.035%に上昇、金利上昇で暮らしはどう変わる?

【画像出典元】「MeshCube/Shutterstock.com」
監修・ライター
5月28日の国内債券市場で長期金利の指標となる10年債利回りが1.035%に上昇しました。2012年4月以来、およそ12年ぶりに高い水準です。市場関係者の間では大きなインパクトを持って受け止められたこのニュースですが、「長期金利と聞いてもピンとこない」という方も多いのではないでしょうか。そこで本稿では長期金利とは何か、長期金利が上がると私たちの生活はどう変わるのかといったところを分かりやすく解説したいと思います。
長期金利はおよそ12年ぶりの高水準に
5月20日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年債利回りは0.975%に上昇しました。2023年11月1日に付けた0.95%を超え、2013年5月以来となる11年ぶりの高水準となりました。長期金利の上昇局面はその後も続き、5月28日の債券市場では午前の取引で10年物国債の利回りが1.035%を付け、2012年4月以来、およそ12年ぶりに高い水準となっています。
「長期金利」は新聞やテレビなどのニュースでよく使われることもあり、言葉自体は知っているという方も多いのではないでしょうか。しかし、長期金利とはどのようなもので、どういったタイミングで上がるのか、長期金利が上昇すると私たちの生活にどのように影響を及ぼすのかといったことを説明できる方は案外少ないのではないでしょうか。そこで本稿では長期金利について分かりやすく解説したいと思います。
金利はなぜ上げ下げする?

長期金利の説明に入る前に、まずは金利がどういうものなのかを整理していきましょう。
金利とは、お金を貸し借りする際に発生する手数料のようなものです。金利は常に一定ではなく、商品やサービスの価格のように、需要と供給のバランスによって決まります。例えば、景気が良くなると個人消費が拡大するため、企業は商品をより多く生産し、設備投資への意欲も増加。資金需要が高まるため、金利が上昇することが一般的です。反対に、不景気になると消費者の消費意欲が減退するため、企業は商品やサービスの生産を抑えようとします。設備投資への意欲も減退するため、資金需要が低下し、金利は下がると考えられます。
物価によっても金利は上下します。金利と物価はシーソーの関係と言われています。金利が上がると企業はお金を借りづらくなるため、設備投資に消極的にならざるを得なくなります。結果として、企業の成長度合いが鈍り、株価が下がる傾向にあるのです。反対に金利が下がると企業はお金を借りやすくなり、積極的に設備投資を行うなど、事業拡大します。売り上げや利益が上がり、株価が上がるという理屈です。
また、金利は為替相場の影響も受けます。現在、長らく円安ドル高傾向が続いていますが、円安ドル高の場合、海外から物を購入する際の支払代金が増えます。例えば、1ドル=100円の場合、100ドルの物を購入する際に支払う円は1万円ですが、1ドル=150円になると100ドルの物を購入するのに1万5000円を支払わなければなりません。そうすると商品の原材料物価が上昇するため、国内物価も上昇傾向となり金利も上昇します。反対に円高ドル安傾向の中では、国内物価が下落するため、金利も下がるのです。
長期金利とは?上がるとどうなる?

金利についておおよそつかめたところで、今回話題となっている長期金利についてみていきましょう。長期金利とは、金融機関が1年以上のお金を貸し出す際に適用する金利のことです。満期は2年、5年、10年、20年、30年、40年とありますが、新聞やテレビで報じられる長期金利は、10年物国債の金利を指します。
さて、それでは長期金利が上がると私たちの生活にどう影響するのでしょうか。
私たちの生活の中で金利の影響が一番大きいのは住宅ローンではないでしょうか。住宅ローンの種類は全期間固定金利型、変動金利型、固定金利型の3種類に分けられます。このうち、長期金利の影響を受けるのが固定金利型です。長期金利が上がると、固定金利型の住宅ローンの金利も上がります。実際に2022年12月に日銀が長期金利の上限を引き上げたことを受け、大手銀行は10年固定型の住宅ローン金利を引き上げました。住宅ローンの金利が上がれば、トータルの返済額は増えます。
また、長期金利の上昇は企業活動にも大きな影響を与えます。企業は金融機関などから資金を調達して企業活動を行いますが、金利が上昇すれば、資金調達のコストが増加。設備投資など積極的な事業拡大が難しくなります。また、金利上昇分のコストを価格転嫁できなければ、利益も減少してしまいます。企業活動は抑制され、利益が減少した結果、日本全体で今より深刻な不況に陥ってしまう可能性もあるでしょう。
ここまで、長期金利が上がることの負の側面だけを紹介しましたが、何事もそうであるように長期金利の上昇にもメリットはあります。代表的なメリットは、金融機関の定期預金の金利が引き上げられる可能性がある点。また、生命保険の利回りである「予定利率」が引き上げられる可能性もあります。その場合、契約者が受け取るお金が増えたり、保険料が引き下げられたりといったことが考えられます。
長期金利が上がると住宅ローン金利が上がったり、企業活動が抑制されてしまったりと、私たちの生活に大きな影響を及ぼします。金利は外国の金融政策など外的要因を含め、様々な要因で決まるため、長期金利を下げたいと思っても簡単にコントロールできるものではありません。大切なのは、私たち一人ひとりが金利の上昇に備えておくこと。住宅ローンにおいては繰り上げ返済を行ったり、返済計画を見直したりといったことがより重要になってきます。ビジネスにおいては、たとえ金利が上がったとしても持続可能な新たなビジネスモデルを構築しておくことが求められるようになるでしょう。