初任給からこんなに引かれる!新入社員が知っておくべき5つのお金

【画像出典元】「GlooStock- stock.adobe.com」
サラリーマンが毎月給料から天引きされている税金・社会保険料は、大きく分けて5つあります。これらは、私たちの社会保障制度を支える重要な役割を担っているため、責任をもって支払わなければなりません。
今回は新社会人として知っておきたい、給料から天引きされている税金と社会保険料の特徴や仕組みについてまとめてみました。初任給の明細を見て驚く前に確認しておきましょう。
なぜ給料から税金と社会保険料が天引きされる?

サラリーマンになるとなぜ「天引き」が発生するのでしょうか。ここでは天引きの意味や仕組みを解説します。
天引きとは?
「天引き」とは、税金や社会保険料など本人が支払う必要のあるお金を、毎月の給料から自動的に差し引く仕組みのことです。
例えば初任給が20万円(額面での支給額)の会社に入社した場合、税金や社会保険料などで約3万円程度が「天引き」され、実際に振り込まれる金額は約17万円前後となるのです。なお、この最終的に振り込まれる金額のことを「手取り額」と呼びます。
天引きの仕組み:
給料(支給額)ー税金や社会保険料=手取り額
なぜサラリーマンは天引きがあるの?
給料の天引きは労働者のために行われています。というのも税金や社会保険料の支払いというのは手続きや管理に手間がかかるものであり、自分で行おうとすると支払いを忘れたり、支払額を把握できず足りなくなる恐れもあります。
そうした支払い手続きを本人に代わり会社が代行しているのが天引きであり、労働者の手間の削減やトラブル防止のために行われています。
なお自営業者の場合は、こうした支払いに関する計算や手続きを、自分で行うことになります。
アルバイトでも天引きはある?
正社員だけでなくアルバイトやパートでも給料の天引きが行われることがあります。例えば「勤務時間及び日数が正社員の4分の3以上」など、一定の条件を満たせばアルバイトであっても社会保険に加入できることがあります。その場合、正社員と同じように社会保険料などを給料から天引いてくれるのです。
社会人になったら払わねばならない5つのお金

社会人になり会社で働くと、主に以下の5つのお金が毎月の給料から天引かれます。
・所得税
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・住民税
以降でそれぞれの税金・社会保険料の特徴を解説していきますので、理解しておきましょう。
所得税
「所得税」とは、所得の額に応じて支払う税金のことです。サラリーマンであれば「給料所得」が該当します。
所得が高いほど税率が高くなり、課税所得が195万~330万円の範囲であれば税率は10%ですが、695万~900万円の場合は23%、900万~1800万円の場合は33%といったように、所得が増えるほど税率もアップしていきます。
なお所得税は、年末に年間所得が確定するため、毎月の給料から天引かれるのは概算額です。そして「年末調整」により、払い過ぎた分が返ってくることがあります(詳細は後述)。
健康保険料
「健康保険」は、病気や怪我などで医療機関にかかった際の費用を一部負担してくれる制度であり、毎月保険料を支払う必要があります。
健康保険料率は都道府県によって異なり、定期的に改定されています。参考として福岡支部の健康保険料率は10.35%です(令和6年4月納付分より)。仮に給料が20万円の場合、その10.35%分となる2万7000円が月々の健康保険料となりますが、健康保険料は半分を会社が負担する決まりであるため、残りの1万3500円が毎月の給料から天引かれる形となります。
厚生年金保険料
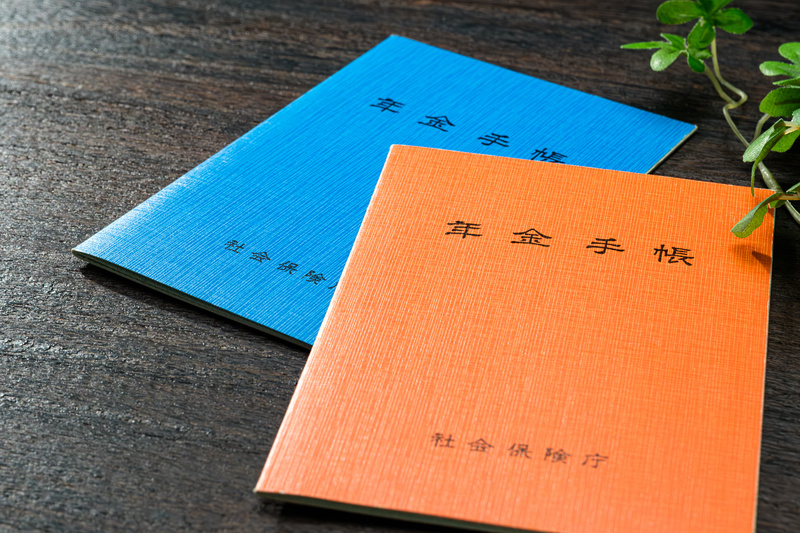
「厚生年金」は、会社などに勤務している人が加入する年金制度です。厚生年金保険の保険料率は、現在18.3%で固定されており、保険料は毎月支払う必要があります。
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
出典:日本年金機構
仮に給料が20万円の場合、その18.3%分となる3万6600円が月々の厚生年金保険料となりますが、健康保険料と同様に、厚生年金保険料も半分は会社が負担する決まりであるため、残りの1万8300円が毎月の給料から天引かれる形となります。
雇用保険料
「雇用保険」は労働者の安定した生活を守るための制度です。失業した際の失業手当や、育児休業や病気などによる休業手当などがこの保険料によってまかなわれており、保険料は毎月支払う必要があります。
雇用保険料率は毎年のように改定されており、最新の令和7年度(2025年度)の雇用保険料は1.45%です(一般の事業の場合)。
仮に給料が20万円の場合、労働者負担分の0.55%分となる1100円が毎月の給料から天引かれる形となります。
住民税
「住民税」は地方税のひとつであり、都道府県や市区町村に対して収める税金です。税率は全国で一律10%(道府県民税 4%+市町村民税 6%)と定められており、サラリーマンの場合、毎月支払う必要があります。
なお住民税は、前年1年間の所得から社会保険料控除や医療費控除、生命保険控除等の所得控除を引いた額として計算します。仮に給料が20万円の場合、単純にその10%となる2万円となるわけではなく、各種控除を反映させると約7000円前後が毎月の支払額となります。
・マメ知識:住民税は社会人2年目から
住民税は、前年1年間の所得に応じて課税されます。そのため、通常は入社して1年間は住民税の天引きはなく、社会人2年目の6月分の給料より天引きが開始されます。
年末調整について予備知識

会社に勤める場合、給料の天引きとセットで覚えておきたいのが「年末調整」です。ここでは年末調整の仕組みと従業員がやることについて解説します。
年末調整とは
「年末調整」とは、「所得税の過不足を精算する手続き」のことを指します。
所得税はその年の所得額に応じて算出されます。しかし年末(12月末)にならないとその年の所得額ははっきりとしません。そのため、毎月の給料から天引き(源泉徴収ともいう)されている所得税は、あくまで概算額です。
年末になると経理部などが年末調整の作業を行い、正しい所得額で所得税を算出し直します。これにより天引きされた額と差があった場合、還付もしくは追加徴収が行われます。
従業員がやることは?
年末調整では、扶養控除、配偶者控除、保険料控除など、各種控除も含めて所得税を算出します。そのため従業員は以下の書類を会社側に提出し、控除の状況を報告する必要があります。
年末調整で提出する書類:
・扶養控除等(異動)申告書
・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
会社にもよりますが、一般的には10月下旬ごろから年末調整の作業が開始され、年末調整についての連絡と各種申告書が配布されます。そして11月下旬頃を目途に経理部などに提出するのが一般的です。
人によっては申告内容を証明する書類(各種保険料の控除証明書など)の添付が必要になることもあります。年末調整の時期が近づいてきたら、加入している保険会社などから発行されている控除証明書などを整理し、準備をしておきましょう。
以上、給料から天引きされているお金について解説しました。
社会人になると今回紹介した5つの税金・社会保険料を天引きという形で毎月支払っていかなければなりません。また昇進や昇格により給料が上がれば、天引きされる税金や保険料もより増えますので、その分も加味した上で将来の給料や家計のシミュレーションをしていきたいところです。










