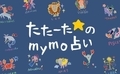海外移住で年金・社会保険はどう変わる?リスクと備えをFPが解説

【画像出典元】「Ivan Marc/Shutterstock.com」
今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、リタイア後の海外移住について、社会保険・年金制度や税務面での影響、さらに移住パターン別のメリット・デメリットについて解説していきます。また、3カ国以上の拠点を持つ非居住者としての税務上の効果についても取り上げます。
50代男性Sさんからの相談内容
将来、リタイアした後に海外移住も選択肢の一つとして考えています。海外移住すると、社会保険や年金の取り扱いはどうなるのでしょうか?今のところ移住先で働く想定ではありませんが、仮に働く・働かないで取り扱いが変わる場合はその内容が知りたいです。また「永住」「10年だけ移住」「配偶者あり・なし」などのパターン別にメリット・デメリットを知りたいです。また、3カ国以上の拠点で非居住者になると税務上有利になるという話を聞いたことがあるのですが、具体的にはどうなのでしょうか?
海外移住に伴う社会保険・年金の取り扱い
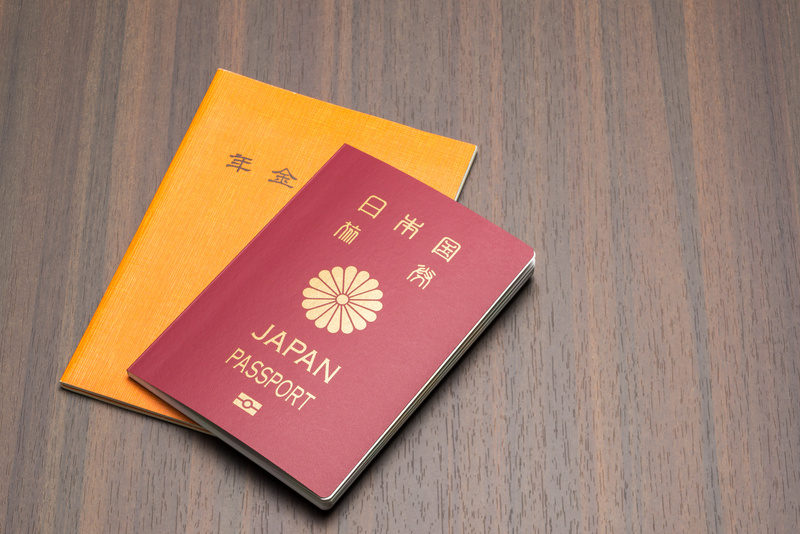
海外へ移住する際、日本の社会保険や年金制度の扱いは大きく変わります。基本となるのは、日本から海外へ住所を移すために海外転出届を提出し、住民票を抜くかどうかです。
1)健康保険・介護保険
住民票を抜くと、国民健康保険および介護保険の被保険者資格は原則として喪失します。これにより、日本に一時帰国した際の医療費は全額自己負担となります。
限定的な救済措置として海外療養費制度がありますが、これは日本の診療報酬基準で払い戻し額が計算されるため、現地の高額な医療費を十分にカバーできるとは限りません。また日本と現地の医療制度に差があるため、払い戻しは申請手続きが煩雑かつ時間がかかります。そのため、移住先で現地の公的医療保険に加入するか、民間の海外居住者向け医療保険に加入することが不可欠でしょう。
2)公的年金制度
年金は健康保険とは異なり、海外移住後も関係を継続する選択肢があります。
国民年金:
海外に移住すると加入義務はなくなりますが、任意加入制度を利用して保険料を納め続けることができます。任意加入することで、将来の年金受給資格(原則10年以上)を満たしたり、受給額の減少を防いだりすることが可能です。すでに年金を受給している場合は、海外に居住していても引き続き受け取ることができます。
厚生年金:
過去に会社員として加入していた期間に基づく受給権は、海外に移住しても維持されます。将来、受給開始年齢に達すれば、海外に住んでいても年金を受け取ることが可能です。
就労の有無による影響

移住先で働くか働かないかによって、社会保障の取り扱いは大きく異なります。
1)働かない場合
基本的には移住先国の社会保険制度への加入義務はありません。収入源は主に日本の年金給付や個人の資産となり、日本の年金制度(任意加入の有無)を軸に将来設計を考えることになります。
2)働く場合
移住先で雇用されると、その国の社会保障制度(年金・医療保険など)への加入が求められることが一般的です。この時問題となるのが、日本と移住先国での社会保険料の二重払いです。
この二重払いの問題を解決するのが社会保障協定です。日本はアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなど主要国を含む23カ国と社会保障協定を結んでいます(2025年9月時点)。
協定国で働く場合は、二重加入の防止や両国の年金加入期間通算などが可能になります。ただし協定がない国では、保険料が掛け捨てになるリスクもあるため、事前の確認が不可欠です。
移住パターン別のメリット・デメリット
移住期間や家族構成によって、考慮すべき点が大きく異なります。
1)永住移住の場合
メリット:
・生活基盤を完全に移すことで、移住先国の社会保障や医療・介護サービスを本格的に活用できる
・物価の安い国を選べば、日本の年金収入でも経済的にゆとりのある生活を送れる可能性がある
・移住先国の税制優遇措置を長期的に活用できる場合もある
デメリット:
・日本の社会保障制度から完全に離脱するため、将来日本で高度な医療や介護を受けたくなった場合に対応が難しくなるリスクがある
・年金を海外で受け取る際、長期間にわたり為替変動リスクを負うことになる
・相続が発生した場合、両国の法制度にまたがるため、手続きが複雑になる可能性がある
2)10年限定移住の場合
メリット:
・将来日本へ帰国することが前提のため、帰国時に日本の社会保障制度へ比較的スムーズに再加入できる
・海外生活を試すことができ、合わない場合は帰国するという柔軟な計画が立てられる
・ライフスタイルの多様化を図りながら、一定期間の非居住者期間を活用した税務上のメリットを享受できる可能性がある
デメリット:
・移住期間中、日本の社会保障に空白期間が生じやすくなる。国民年金の任意加入を怠ると、将来の年金額が大幅に減る可能性がある
・住民税や所得税の取り扱いが複雑になりがち
・帰国後の住居の確保や、日本の生活への再適応が課題となる場合がある
3)配偶者の有無による違い
配偶者がいる場合:
夫婦それぞれの年金受給権や健康状態、移住への意向を総合的に検討する必要があります。一方が日本に残る場合は、世帯分離による税制上の影響や健康保険の扶養関係の整理も必要です。夫婦で支え合いながら新生活に臨める精神的なメリットがある一方、どちらかの適応が難しい場合にストレスとなる可能性もあります。
単身の場合:
移住先やライフスタイルを柔軟に決められる自由度の高さがメリットです。その一方で、病気や怪我など緊急時の対応体制を一人で構築する必要があり、医療・介護リスクへの備えが一層重要になります。また現地で孤立しないよう、コミュニティとのつながりを意識的に作ることも課題となります。
複数国拠点による税金の取り扱い

ご質問の「3カ国以上の拠点で非居住者になると節税になる」というお話は、国際税務におけるタックス・レジデンス(税務上の居住地)の考え方に関連します。
1)理論上の考え方
日本の税法では、国内に住所または1年以上の居所を持つ個人を居住者とみなし、その人の全世界所得に課税します。一方、非居住者は日本国内で得た所得(国内源泉所得)のみが課税対象です。
タックス・レジデンスはこの仕組みを利用し、どの国においても年間滞在日数を一定(例⇒183日)未満に抑えるなどして、いずれの国でも税務上の居住者と認定されない状況を作り出すことで、税負担を軽減しようという考え方です。
2)4つのリスクと課題
理論的には可能に見えますが、現在の国際的な税務環境では、この方法を実行するのは非常に難しく、大きなリスクが伴います。
実態の重視
各国の税務当局は、滞在日数のような形式的な基準だけでなく、住居の場所、家族の居住地、経済的な利害関係の中心地といった生活の実態を総合的に見て居住地を判断します。
国際的な情報交換
CRS(共通報告基準)により、世界各国の金融機関は口座情報を自動的に各国の税務当局と交換しています。これにより、複数国に資産を分散させても、税務当局は個人の資産状況を容易に把握できる仕組みを作っています。
租税回避への監視強化
近年、国際的な租税回避に対する取り締まりは世界的に強化されており、意図的な非居住者戦略は租税回避と認定され、重い追徴課税を負うリスクがあります。
生活上の不便
居住地が定まらないと、銀行口座の開設や各種契約が困難になるなど、安定した生活基盤を築く上で大きな支障が生じる可能性があります。
結論として、この方法はごく一部の富裕層が専門家のチームに相談しながら慎重に進めるものであり、一般の方が軽い気持ちで実行するのは非常にリスクが高いと言えます。
まとめと成功へのアドバイス
海外移住は、単なる引っ越しではなく、ご自身の社会保障、税制、資産、そしてライフプラン全体に関わることです。検討する上で必要なことを下記にまとめます。
準備期間を設ける
移住先の選定から手続きまで、最低でも2~3年の準備期間を設けることをお勧めします。
目的を明確にする
生活コストの削減、温暖な気候、新たな挑戦など、移住の目的と期間を明確にすることが、最適な国選びの第一歩です。
専門家と連携する
海外移住計画は、国際税務に詳しい税理士など、各分野の専門家と連携しながら進めることが不可欠でしょう。
現地を体験する
可能であれば、移住候補国に短期滞在し、現地の生活環境や文化を肌で感じてみることが、ミスマッチを防ぐ上で非常に有効です。
ご自身の豊かな人生設計のために、ぜひ時間をかけて慎重にご検討ください。
※本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の選択を推奨するものではありません。個別事情により取り扱いが異なるため、最終的な判断は各国の最新制度・条約および専門家の助言に基づきご自身でご決定ください。