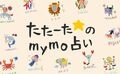老後資金は何歳まで想定すべき?資産計画のコツをFPが解説
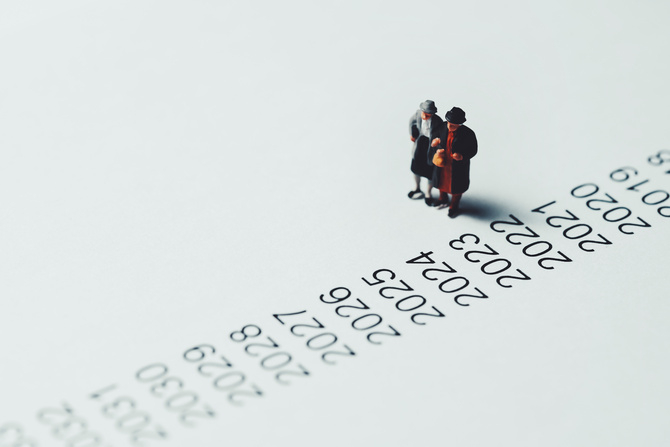
【画像出典元】「stock.adobe.com/beeboys」
目次
今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、50代男性から老後のプランに関するご相談です。ライフプランやキャッシュフロー表など、老後のプランを作成する時に何歳まで生きる前提で作るのが良いのか?シンプルでありながら非常に奥深い、難しい質問です。これまでライフプランの作成やFP相談に応じてきた経験から、老後資産の管理法や考え方について回答します。参考にしてください。
50代男性Rさんの相談内容
今まである程度の貯蓄はしてきたのですが、相続により親からの財産を引き継ぎました。資産面でさらに余裕ができ、人生計画においても解像度がより上がったのですが、自身が死ぬまでの資産計画を立てていて疑問が芽生えました。
みなさん何歳まで生きる前提で計画を立てているのでしょうか? 私の場合は独身なので、78歳で亡くなってだいぶ余るのも嫌ですし、仮に85歳までで計画を立てていて95歳まで生きた場合など、かなり高齢になってから「お金がない」という状況はもっと嫌だと感じています。資産計画・管理の観点から良きアドバイスがあれば教えてください。
老後の資産管理は「取り崩し」が前提

老後に関しては「どうやって老後資金を貯めるか?」という相談が非常に多いです。Rさんのように潤沢に資産があり、独身であるため後に残すこともなく上手に使い切りたいというのは、意外と老後の資金を貯めるよりも難しいのでは?と感じています。
その理由が2つです。
・いつまで生きるか分からない
・将来が不安で思い切って取り崩せない
どちらもRさんの相談内容に重なるところですが、一つはゴールが見えないことで「いくら取り崩して良いか分からない」という点です。もう一つは「毎月〇万円、取り崩しても大丈夫」と分かっていてもなかなか取り崩すことができず、結局亡くなった時が今までで一番資産額が多かったというケースも少なくありません。これは、資産管理に保守的と指摘されている日本人ならではかもしれません。
実際、相続人が不在で国庫に入る財産は10年で3倍に増え、初めて1000億円を超えたとの報道もあります。もちろんRさんはそれを望んでいませんので、上手に資産を取り崩しながらセカンドライフを満喫してもらいたいです。
老後プランは平均寿命より「平均余命」
「何歳まで生きる前提でライフプランを考えるのか?」というのは非常に難しいところですが、平均寿命ではなく「平均余命」を参考にするのが良いと思います。
平均寿命は子どもの頃に亡くなるというケースも含まれます。よって例えば55歳の場合、厚生労働省の資料から約28年が平均余命です。少し長めに見て30年、85歳まで生きることを大前提にライフプランを考えておけば大きな誤差は生じないと思います。
参考:厚生労働省「主な年齢の平均余命」
「リアルオプション」理論でライフプランを考える

大規模な事業やプロジェクトの場合は、どれだけお金を投じるか、どの状況になれば撤退するかなどを綿密に決めながら進めていきます。その際に「リアルオプション」という理論が活用されることがあります。この理論をライフプランの参考にしてみるのはいかがでしょうか。非常に複雑な理論であるため、以下、簡易にしたものを紹介します。
「楽観・標準・悲観」の3つのシナリオを想定してみました。

楽観・標準・悲観はそれぞれ考え方や価値観は異なって良いと思います。本来、長生きできることは良いことと捉えたいところですが、上の例では90歳までやや大変な状況で生きることを悲観シナリオにしてみました。
そして例えばこの3つのシナリオでライフプランを作り、65歳から必要な資金を計算します。加えてそれぞれ起こりうる確率を定めることで必要な老後資金を算出します。
例)シナリオ別ライフプランの例

(必要な老後資金の目安)
2000万円×20%=400万円
3000万円×60%=1800万円
4500万円×20%=900万円
各シナリオの400万円+1800万円+900万円=計3100万円を必要な老後資金と考えます。実際のリアルオプションは「この状態になるとプロジェクトから撤退する」といったシナリオも描きますが、人生で撤退はできませんので、あくまで簡易的にあまり複雑にならない範囲で描いてみることをおすすめします。
3つのシナリオの発生確率も自分で決めることになりますので、なかなか難しいところですが、自分自身と向き合う良い機会と捉えてみるのはいかがでしょうか?
ライフプランは「長期」と「目先3年」を組み合わせて
筆者もこれまで数多くのライフプランを作成し、アドバイスをしてきました。そしてその後5年後、10年後を迎えた方々と見直す機会もありましたが、全員がライフプラン通りには進んでいません。
全く予定していなかった転職をした人、見込んでいた子どもの人数が違う人、そして離婚をしたケースなど、やはり将来の不確定要素は多いということを感じています。
よって「長期的にはラフなプランを描き、目先3年前後のライフプランを詳しく数値化する」というやり方が効果的だと感じています。そしてその3年程度のライフプランを、定期的に更新をしていく。更新するたびにライフプランと向き合うことになり、ご自身の考えや価値観が以前より変わっていることに気付くこともあるでしょう。
具体的に〇歳までライフプランを作りましょう、とあえて断言はしていません。今回紹介した考え方などを参考にRさんらしい未来を描いてください。
もちろんライフプランを描きながら将来の準備をすることも大切ですが、同様に今もとても大切です。優先順位をつけながら日々生活していきたいですね。