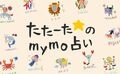60歳前に死亡したらiDeCoはどうなる?離婚・破産のケースも解説

【画像出典元】「stock.adobe.com/tiquitaca」
目次
iDeCo(個人型確定拠出年金)はNISAと並んで大きな税制メリットがあり、老後資金作りに役立つ制度として知られています。「60歳まで引き出せない」というのが大きな特徴の一つですが、「もし60歳までに死亡したら?」「離婚や自己破産の時はどうなるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。
今回は死亡や離婚、自己破産した場合などのiDeCoの取り扱いについて解説していきます。
iDeCoの特徴とメリット、NISAとの違いもおさらい
iDeCoは個人型確定拠出年金と呼ばれるもので、老後資金を自分で積み立てていくことができる制度です。iDeCoの主な特徴は以下の通りです。
●自分で積み立てと運用を行う
毎月一定額を積み立て、その資金を自分自身で選んだ金融商品で運用します。
●税制メリット
積立時:掛金が全額所得控除になります。
運用時:運用益に課税はされません。
受取時:一時金で受け取る場合は退職所得として「退職所得控除」、分割で受け取る場合は雑所得として「公的年金等控除」ができ、税負担を軽減して受け取ることができます。
●長期積立
一定の金融商品からリスクとリターンを考慮して自分に合った商品を選び、原則60歳まで積み立てを続けることで、複利効果による資産形成が期待できます。途中見直しを行うことも可能です。
NISAと混同する人も多いですが、NISAはあくまで投資を行う上で配当金や譲渡益が非課税になるという制度でいつでも売却、換金ができます。もちろん老後資金準備としてNISAを利用してもいいですし、教育資金準備や将来の旅行のためといった様々な目的を設定して投資を行うことができます。
一方iDeCoは「年金」とあるように明確に老後を目的としており、NISAにはない税制メリットや制限などが設けられている点が大きな違いです。
加入者が死亡した場合のiDeCoは「死亡一時金」に

加入者が死亡した場合は遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。死亡一時金を受け取ることのできる遺族は民法の定める相続の順位とは異なり、法令に基づく受取人の順位は以下の通りです。
(1)配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
(2)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)(2)の者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、(2)のものに該当しない者
参考:JIS&T(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)HPより一部抜粋
配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の中から、あらかじめ死亡一時金受取人を指定することができます。その際は運営管理機関、つまりiDeCo口座を開設している金融機関で手続きを行います。ネット上で受取人の指定や変更を行うことができる金融機関もあるので、一度確認してみてください。
なお、遺族が死亡一時金を受け取る場合、遺族からの申し出が必要となります。加入者等死亡届を運営管理機関に提出するといった手続きが必要となります。その他、受取人の印鑑証明書や受取人のマイナンバーカード、死亡した人と受取人の関係を証明する戸籍謄本などが必要となります。
死亡してから5年間請求がない場合、受給権者がいないとみなされ受け取れなくなる場合があるので早めに運営管理機関に連絡をし、手続きを行いましょう。手続き完了後、受取人の指定口座に死亡一時金が振り込まれることになります。
死亡一時金の金額ですが、iDeCoは加入者の運用方針により投資信託等で運用しているため日々残高は変動します。死亡した日の残高ではなく手続きが完了した時点での残高となるため、手続きを行うタイミングで死亡一時金の額が変動します。
死亡一時金に対する相続税の課税は?
次に死亡一時金の課税関係について紹介します。死亡一時金は請求するタイミングによって課税関係が異なります。死亡日から3年以内に死亡一時金の支給が確定した場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。一方で3年を超えた場合、受取人の一時所得として所得税・住民税の対象となります。それぞれ簡単な事例を紹介します。
〇死亡日から3年以内の場合…みなし相続財産として相続税の対象
みなし相続財産とは「亡くなった人が保有している金融資産や不動産とは異なり、本来は相続財産ではないものの、税法上、相続財産として相続税の対象にする」というものです。生命保険金や死亡退職金などもみなし相続財産に該当します。
みなし相続財産の場合、500万円×法定相続人の数が非課税扱いとなります。
相続人が妻、子ども2人の場合
500万円×3=1500万円…非課税枠
iDeCoは掛金に上限があるため、仮に月額2万円を拠出している場合、20年でも拠出額の総額は480万円です。それに運用益を考慮しても非課税枠があるため相続税はそれほど気にする必要は無さそうです。
また相続税は3000万円+600万円×法定相続人の数が基礎控除となります。
相続人が妻、子ども2人の場合
3000万円+600万円×3=4800万円…基礎控除
よって、死亡一時金が仮に非課税枠を超えても基礎控除の範囲内であれば一切相続税は課税されません。
〇死亡日から3年超の場合…一時所得として所得税・住民税の対象
死亡保険金の受け取り確定が3年を超過した場合、受取人の一時所得となります。一時所得は特別控除が50万円あり、また他の所得と合算する際に2分の1にできますが、相続税に比べると税負担が重くなる可能性が高いです。
死亡日から4年後に死亡一時金300万円を受け取った場合
(300万円-50万円)×1/2=125万円…総所得金額として他の所得と合算
※必要経費等はゼロとして計算しています
給与所得など他の所得との兼ね合いがありますが、仮に所得税・住民税どちらも10%ずつであった場合、上のケースですと所得税12万5000円、住民税12万5000円、合わせて25万円となります。
このように手続きに時間がかかると思わぬ税負担が生じてしまう可能性があります。iDeCoに加入している方はできれば受取人を指定しておき、その受取人に「万が一の際は早めに死亡一時金を〇〇銀行(証券など)に連絡をして手続きをしてほしい」と伝えておきましょう。
離婚した場合、iDeCoは財産分与の対象となる?
離婚した場合、預金など結婚後の収入がベースとなっている資産は財産分与の対象となりますが、iDeCoはどうなるのでしょうか?
iDeCoも預金などと同様に原則として財産分与の対象となります。もちろん結婚後に掛金を拠出した分が対象となります。ただし、iDeCoの場合は60歳以降にならないと受け取れないといった特殊な要因があります。
例えば30歳夫婦が離婚した場合、その時点で受取額が確定していないため「財産分与の評価額をどうすべきか」といった問題が生じます。また掛金自体がその時点で少額であるケースも考えられますので、弁護士など法律家、専門家に相談するのが良さそうです。
自己破産したらiDeCoは差し押さえられる?
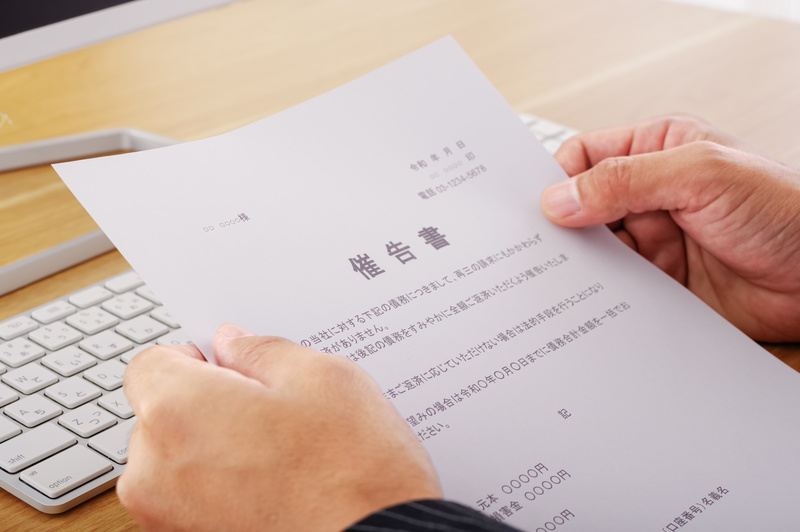
では自己破産した場合、iDeCoはどうなるのでしょうか?確定拠出年金法32条に以下のように定められています。
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文に「給付を受ける権利は差し押さえることができない。」とあるように、60代以降の給付のために30代や40代で拠出している段階で自己破産したとしても差し押さえられることはありません。
ただし法律にも明記されているように、必ず給付を受けられるわけではありません。将来、給付を受ける際などに差し押さえられる可能性があります。
なおNISAや個人年金保険などは差し押さえられる可能性があります。iDeCoやNISA、個人年金などで目的意識を持ってしっかり資産形成をしている人が自己破産になることは考えにくいですが、ちょっとした油断や付き合いでのギャンブル、身元保証人になるといった自己破産の引き金となりそうな要因はいくつかあります。差し押さえられる可能性があるかどうかに関わらず、くれぐれも気を付けてください。
iDeCoをはじめ、万が一に備えて家族とお金の情報共有を
長寿国日本。9割近くの人が65歳以上まで生きる(※)と言われています。よって、iDeCo加入中に亡くなるケースはそれほど多くないでしょう。健康に60代に突入し、現役時代にコツコツと続けてきたiDeCoを一時金や年金形式で受け取り、「セカンドライフを楽しむぞ」と前向きに老後と向き合いたいものです。そのためにも少しでも多く拠出し、上手に運用して増やしたいと思っている人も多いでしょう。
※厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況」を参照
ただし、今回取り上げたような予期せぬ事態まで想定してiDeCoへの加入や掛金額を考えている人がどれだけいるでしょうか?かく言う筆者もそういった事態をそれほど想定せずiDeCoに加入しています。
例えば、死亡ではなく所定の障害者になった場合にも「障害給付金」をもらうことができます。交通事故や病気で何年も寝たきりになるということも考えられます。そんな時にやはり家族や大切な人がしっかりと情報を共有していれば、それぞれ迅速に対応することが可能となります。
何年も手続きをしないと様々な面で不利益を被る可能性があります。iDeCoに限らず、今はネットやスマホでも様々な金融取引ができるため、通帳や書類、郵送物などを通して取引実態を把握しづらくなっています。ぜひこれを機にiDeCoに加入している方は万が一に備えて受取人となる方と一度ゆっくり話をする機会を設けてください。
iDeCoに関連するQ&A
Q:iDeCoの掛金をベースにお金を借りることはできますか?
A:できません。生命保険やiDeCoと同様の制度でもあり個人事業主が加入できる小規模企業共済では契約途中で貸付を受けることができる制度がありますが、iDeCoにはそのような制度はありません。
Q:国民年金や厚生年金などは自己破産した場合、どうなりますか?
A:公的年金である国民年金と厚生年金、どちらも自己破産の影響を受けることなく、将来受け取ることができます。もちろん保険料の滞納を長く続けている場合などはもらえない可能性があるため、自営業など第1号被保険者の方で保険料納付が困難な場合は免除手続きを行ってください。