経済学者の約7割が高校無償化の拡大に反対?その理由を探る

【画像出典元】「stock.adobe.com/William W. Potter」
監修・ライター
日本では教育の機会均等を目指し、高校授業料の無償化が進められています。しかし、最近の調査では経済学者の約7割が無償化の拡大に反対していることが明らかになりました。なぜ専門家たちは無償化拡大に否定的な立場を取るのでしょうか。本記事では、反対意見の背景とその理由について詳しく探ってみました。
高校無償化の議論が再燃
高校無償化とは、一定の所得基準を満たす家庭の高校生に対して授業料を給付する国の制度です。2010年に始まり、2020年4月からは私立高校も実質無償化されました。具体的には公立高校では年収910万円未満の世帯の子どもを対象に年間約11万9000円、私立高校では年収590万円未満の世帯の子どもを対象に最大約39万6000円が支給される仕組みになっています。
政府・与党と立憲民主党、日本維新の会の3党は、高校無償化のさらなる拡大に関する合意を交わしました(2025年3月時点)。この合意により、2026年度から以下の変更が予定されています。
・所得制限の撤廃
これまで年収910万円未満の世帯が対象だった収入要件が撤廃され、すべての家庭が無償化の対象となります。
・私立高校の支給額引上げ
私立高校の就学支援金が全国平均の45万7000円に引き上げられます。
また、先行措置として2025年度分では、公立・私立問わず全ての世帯に対して年間約11万9000円を支給し、収入要件を事実上撤廃することが決定されています。
これらの施策は、教育の機会均等や子育て支援の強化を目的としていますが、一方で財源確保の問題や公平性の観点から反対意見も少なくありません。
日本経済新聞が行った調査では、経済学者の約7割がこの政策に「反対」と答えたそうです。なぜ、これほど多くの専門家が批判的な見方をしているのでしょうか。
高校無償化の拡大が反対される3つの理由

高校無償化の拡大に対しては、経済学者に限らず多くの反対意見が挙がっています。その理由は、主に以下の3つが挙げられます。
1.効果の不透明性
特に収入の少ない家庭の子どもたちには、無償化政策が始まる前から授業料補助制度が存在していました。そのため、追加の無償化がどれほど効果的なのかは不透明です。
もし無償化がすべての家庭に適用されると、中間層や富裕層の家庭にも同じ支援が行われることになります。これは、支援の必要性が低い家庭にも税金が投入されることを意味し、結果的に財源の使い方としては非効率であるとの指摘があります。
また、無償化が教育の質の向上に繋がるわけではありません。無償化の財源が学校設備や教員の待遇改善に充てられない場合、結果として教育の質が低下する恐れがあります。教育の質を高めるためには、カリキュラムの改善や教員の研修制度の充実など、より直接的な施策が必要でしょう。
2.費用対効果の視点
多くの経済学者は、限られた教育予算の使い方として高校無償化拡大以外の選択肢も検討すべきだと考えています。高校無償化の拡大には多額の費用がかかりますが、この予算を別の教育分野に振り向けることでより効果的な成果が期待できるかもしれません。
例えば、幼児教育の無償化や拡充は、長期的に見て社会全体の教育水準を向上させる効果があると言われています。研究によれば、幼少期の教育は子どもの学力に大きく影響し、将来の収入にも関わってきます。このため、高校よりも幼児教育にお金を使った方が、社会全体にとって効果的な可能性があるという意見があるのです。
また全員対象の無償化ではなく、本当に支援が必要な家庭に低利子または無利子の奨学金を提供する方法も選択肢の一つに挙げられます。こうすることで、より公平で持続可能な教育支援が実現できるとされています。
3.恒久的な財源の確保
高校無償化政策の拡大は、国の財政に影響を与える可能性もあります。政府が無償化のための資金を確保するには、税収を増やすか他の分野の予算を削減しなければなりません。しかし日本はすでに社会保障費や少子化対策、インフラ整備など、多くの分野で財政的な課題を抱えています。そのため高校授業料の無償化が本当に優先されるべきなのか、疑問を持つ経済学者が多いのです。
また無償化の財源確保のために増税が必要であるとして、消費税や所得税の引き上げが議論されるかもしれません。増税は低所得層を含むすべての国民に負担を強いることになるのではないかといった懸念もあります。
高校無償化の拡大に賛成する意見もある
高校無償化の拡大には多くの反対の声が挙がっていますが、賛成する意見もあります。
教育機会の公平性という視点
高校無償化の拡大には多くの反対の声が挙がっていますが、教育機会の公平性という観点から賛成する意見もあります。
現在の制度では年収によって支援の対象が決まっている一方、実際には同じ年収でも家庭ごとに経済的困難度が異なるケースも少なくありません。例えば、同じ収入でも家族構成や医療費、介護負担などによって教育費の負担感は大きく変わるため、単純な年収制限では十分に対応できないこともあるでしょう。
加えて、無償化により高校進学のハードルを下げることで、進学率の向上に繋がる可能性もあります。現行制度では、一部の家庭が支援から外れることで進学を断念するケースも考えられますが、無償化が拡大されれば、より多くの子どもたちが高校教育を受ける機会を得られるかもしれません。
少子化対策としての側面
日本の少子化問題の一因として、子育ての経済的負担が挙げられます。高校授業料の無償化はこの負担を軽減し、子育て世帯の不安を和らげる可能性があります。これは教育機会の拡大だけでなく、少子化対策としても期待されています。
特に大学進学を視野に入れた家庭では、高校の学費負担が軽減されることで、子どもの教育に対する不安が和らぐでしょう。
高校無償化の拡大は本当に最善の策か?
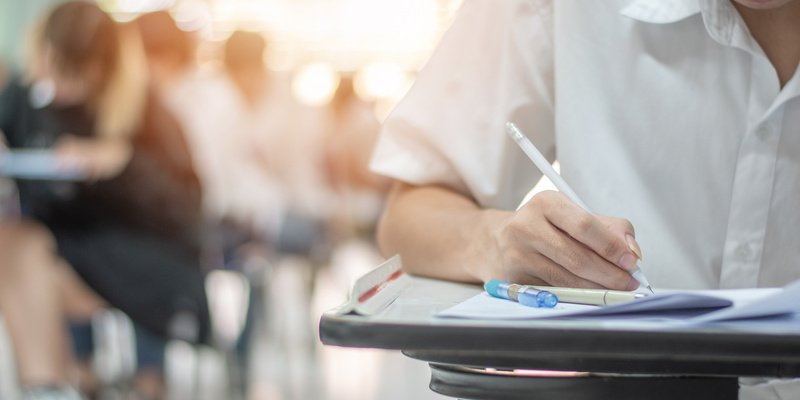
高校無償化の拡大は、教育の機会均等や少子化対策として一定のメリットがあります。しかし、経済学者の多くが指摘するように、財政負担の増大や効果の不透明性、教育政策の優先順位の問題など、多くの課題も抱えています。
筆者自身、高校無償化の理念そのものには一定の価値があると考えます。教育は社会の基盤であり、将来的な経済成長や国の競争力向上に貢献するものだからです。しかし、その実現には慎重な政策設計が欠かせません。単に「無料で学べるのは良いことだ」という視点だけでなく、「その財源はどこから来るのか?」「本当に必要な人に支援が行き届くのか?」といった点を考慮することが大切です。
より効果的な教育政策を実現するためには、高校無償化以外の選択肢も含めて、慎重に検討する必要があるでしょう。










